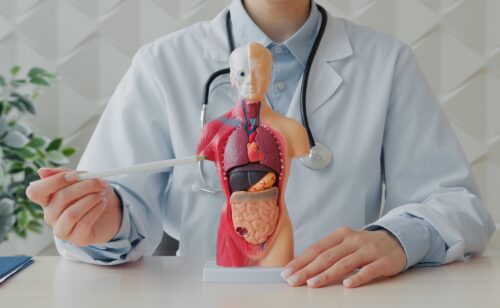日本の医療は、日常では本人の意思が十分に言語化されないまま進みやすい一方で、最終局面になると、本人や家族に「決めること」が求められます。
私はこのねじれが、延命治療の意思決定とACPをかみ合わせにくくしていると感じています。さらに日本では今も、ACPを「延命治療をするかしないかを決めるもの」と誤解する見方が根強く残っています。
私は30年、認知症ケアと看取りの現場に立ち、500名以上の人生の最終段階に関わってきました。その中で何度も、ACPと延命治療の意思決定が、かみ合わないまま進んでいく場面を見てきました。
このズレは、誰か一人の問題ではありません。制度、医療文化、家族心理が重なって生まれるものです。
「選択肢はあります」と言われたとき
終末期の医療現場では、ある時点で必ず家族が呼ばれます。そして医師から、こう説明されます。
- 経管栄養という方法があります
- 点滴で水分を補うこともできます
- 何もしない、自然に任せるという選択もあります
これは、医学的には正しい説明です。医師として誠実な態度でもあります。
しかし、その瞬間から、ACPと延命治療の「ズレ」が始まります。なぜなら、この問いは、ACPそのものではないからです。
ここで家族が受け取るのは、「説明」よりもむしろ、“決断を引き受ける場”に呼ばれたという感覚です。
それは「人生の問い」ではなく「医療の選択」
ここで問われているのは、
- この治療をするか
- しないか
という、医療行為の選択です。
けれどACPが本来扱うのは、
- どんな人生を生きてきたか
- 何を大切にしてきた人なのか
- 苦痛と安心、どちらをどう考える人なのか
という、価値観の共有です。
価値観が共有されていないまま、選択肢だけが提示される。その結果、家族はこう感じます。
「選ばされている」
「決めさせられている」
この違和感は、家族の“気持ちの弱さ”ではありません。価値観の土台がないまま、答えだけ求められているから起きる当然の反応です。
ACPがあっても、機能しない場面
最近になって、「ACP」という言葉が医療の場でも少しずつ聞かれるようになりました。
けれど、終末期の現場で当たり前に共有・参照されているかというと、まだ道半ばです。
現場では、こんなケースが少なくありません。
- 書類はあるが、内容を誰も知らない
- 何年も前に書かれ、状況と合っていない
- 延命治療の可否だけが丸で囲まれている
これでは、ACPがあっても支えにはなりません。ACPは「はい/いいえ」を残すためのものではなく、その人が考え続けてきた“背景”を共有するものだからです。
たとえば——
「延命はしない」に丸がついていても、
「苦痛が少ないなら水分補給は望む」人もいれば、
「管につながれること自体が耐え難い」人もいる。
同じ丸印でも、中身はまったく違います。
ACPが必要なのは、丸の外側にある言葉なのです。
家族が背負わされる「決断の重さ」
延命治療の選択が迫られるとき、多くの家族は同じ言葉を口にします。
「私には、決められません」・・・それもそのはずです。
- 生かすことが正しいのか
- 苦しませてしまうのではないか
- 何もしないことは、見捨てることなのか
この問いに正解はありません。
にもかかわらず「決めてください」と言われた家族は、その選択を 一生背負うことになります。
そして、この“背負わされる感覚”は、家族の心を追い詰めるだけでなく、ときに医療者との関係まで壊してしまいます。
(「先生が決めてくれればよかったのに」という怒りや後悔が残ることもある。)ACPが「延命治療をどうするか」という形でしか理解されていないと、この負担は軽くなりません。
本来、ACPが果たすべき役割
ACPがきちんと機能しているとき、意思決定の場はこう変わります。
- 「本人は、こういう人でした」
- 「こういう時間を大切にしていました」
- 「苦しいことは、あまり望まない人でした」
選択はゼロから決めるものではなく、その人の人生をたどる延長線になります。結果として選ばれる医療が、延命であっても自然であっても、それはACPに反しません。大切なのは、「なぜ、その選択に至ったのか」が共有されていることです。
言い換えれば、ACPは「答えを出すための会議」ではなく、“その人らしさを医療の場に持ち込むための対話”なのです。
なぜ日本では、ズレが埋まらないのか
このズレがなかなか解消されない背景には、日本の医療構造があります。
- 治療を「する/しない」で整理される
- 数値や手技が中心になる
- 時間をかけた対話が評価されにくい
ACPは、時間と関係性を必要とする営みです。それを急性期医療の文脈に押し込めようとすると、どうしても「延命治療のチェック項目」のようになってしまいます。
さらに、家族側にも文化的な壁があります。
「本人に縁起でもない話をさせたくない」
「本人は弱るから聞けない」
「医師に任せた方が安全」
こうした“配慮”が、結果として 対話の空白を生みます。
そして空白のまま、最終局面に入ってしまう。そこで初めて「決めてください」と言われ、家族が崩れていく。この流れが、残念ながら繰り返されています。
私が、ACPを語り続ける理由
私は、延命治療そのものを否定したいわけではありません。苦しみを和らげ、命をつなぐ医療が必要な場面も確かにあります。ただ、その医療がその人の人生とつながっているかそれだけを問い続けたいのです。
ACPは「決めるための道具」ではありません。迷いを、一人で抱え込まないための対話。
人生を、医療の中で見失わないための視点。それがACPです。
おわりに:ズレを埋めるのは、対話しかない
延命治療の意思決定とACPのズレは、制度を整えただけでは埋まりません。
- 日常の中で
- 元気なうちから
- 完璧でなくていい対話を重ねる
それしかありません。私は500人の看取りの中で、その確信を深めてきました。ACPは「選択を迫られる瞬間」のためではなく、その瞬間を迎えたとき、一人にならないための準備です。
このことが、もっと自然に語られる社会になることを、心から願っています。