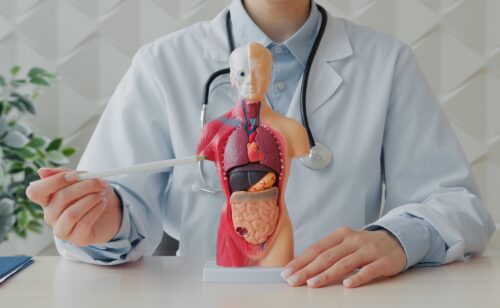認知症高齢者の終末期ケアと「どう生きるか」を考える時間
先日、看護大学にて「認知症高齢者における終末期ケア ― アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」について講義を行いました。
講義を通して私が最も嬉しかったのは、学生の皆さんが“話の表面”ではなく“本質”を受け取ってくれたこと。そして自らの生き方や看護観にまで思索を深めてくれたことでした。
日本は「多死社会」へ――ACPが必須となる時代
講義の冒頭では、日本社会が確実に迎える未来について共有しました。2040年には年間166万人が亡くなる「多死社会」になり、高齢者・認知症高齢者の数も増加し続けます。
高齢化は単なる数字の増減ではなく、生き方・死に方を誰もが考えざるを得ない社会への移行を意味します。ACPは、こうした社会の変化に対する「備え」でもあります。まだまだ国民への周知は十分ではありませんが、むしろこれからの時代には、誰もが向き合っていく必然のテーマなのです。
学生からはこんな感想がありました。「この話は“医療の問題”ではなく“社会の問題”なのだと気づいた」まさにその通りで、ACPは世代を超えて必要となる“生き方の対話”です。
ACPとは「どう死ぬか」ではなく「どう生きるか」を問い直す時間
スライドで紹介したACPの定義をもとに説明したところ、学生たちは驚きをもって受け止めてくれました。「“最後までどう生きるか”という表現を初めて聞いた。心が動いた」
ACPは医療行為の選択を決めるためだけのものではありません。“その人がどんな価値観で生きてきたのか、何を大切にしてきたのか”を土台にして、これから先を、本人・家族・医療者が一緒に考える対話のプロセスです。認知症ケアでは特に、意思決定が難しくなるため、人生の初期段階からの対話が極めて重要になります。
学生のひとりはこう書きました。「ACPは“死の準備”だと思っていたが、実際は“生きることの準備”だった」。その本質に気づいてくれたことが、私には何より嬉しいことでした。
事例が映し出す「揺れ」と「選択」――Aさん・Bさんの物語
● Aさん(96歳)
Aさんは認知症が進行し、意思疎通が難しいまま施設で生活されていました。肺炎を繰り返す中、家族と施設職員は“看取りの方向性”について話し合いを重ねましたが、その後もAさんは 3年以上にわたり、ほとんど反応のない状態で食事介助を受け続ける日々を過ごされました。学生たちが最も心を動かされたのは、ここでした。
「意思疎通ができない状態で、3年以上食事介助が続くという現実に驚いた」
「Aさんは本当はどんなケアを望んでいたのだろう…と考えさせられた」
Aさんが“何を食べたかったのか”、“どのように生き、どのように最期を迎えたかったのか”
それらは、もはや本人から聞き出すことができません。意思決定ができなくなった後の生活は、
その人の過去の価値観や日常のこだわりが唯一の手がかりになります。
この事例は、ACPを早い段階から始める意義を、学生たちに問いかけるものでした。
● Bさん(75歳)
Bさんはアルツハイマー型認知症を患い、その後、脳内出血や肺炎を繰り返しました。介護を担っていた妻は、病状の経過や今後の予測を十分に説明されないまま、手探りで在宅介護を続けていました。しかし、妻の介護疲労が限界に達し、施設入所を決めた時、Bさんはすでに認知症が末期で意思疎通が全くできない状態 となっていました。学生たちからはこのような感想がありました。
「どの時点でACPを始めるべきだったのか…と考え込んだ」
「奥様が“予測を知らされないまま介護を続けていた”という事実が胸に迫った」
「本人が語れないまま、家族だけが重い決断を背負う苦しさを感じた」
Bさんのご家族、とくに奥様は、病状の経過やこれから訪れうる変化について、ほとんど説明を受けないまま介護を続けていました。そのため、「どの段階で何を選ぶべきか」「どんな未来が来るのか」という見通しを持てないまま、日々の介護だけが重なっていきました。
AさんとBさん
二つの事例は一見まったく異なるように見えますが、共通点があります。それは、「ACPを始めるタイミングを逃すと、本人の意向が分からなくなる」という現実です。
意思疎通ができなくなってしまってからでは、「何が好きだったのか」「どのように生きたかったのか」「どんな最期を望んでいたのか」は、誰にも分かりません。そしてその「分からない」という苦しさを背負うのは、家族であり、ケアに関わる者たちなのです。
学生たちはこの2つの事例から、「ACPは医学だけの問題ではなく、“人の人生そのもの”の問題なのだ」と気づいてくれました。
私が学生に伝えたいこと
今回の講義で学生の皆さんが書いてくれた感想を読み、私は嬉しく思いました。ACPは、まだ日本では十分に浸透しているとは言えません。しかし私は、次のことを何よりも伝えたいのです。
人は死の瞬間まで「生きている」。
死ぬ瞬間まで、人格を持ち、尊厳を持ち生きている。
人は一人では死ねません。必ず誰かの支えが必要です。その支えとなるのは、家族であり、医療従事者であり、その人の人生のそばに立つすべての人”です。だからこそ、その人の思いが伝わっていなければ、本当にその人らしいケアは成り立たないのです。
◆ ケアではなく「ケアリング」を大切にしてほしい
看護とは、単に医療行為としての「ケア(Care)」を提供することだけを指しません。もちろん、清拭、経管栄養、点滴管理、バイタル測定など、目に見える“行為”としてのケアは看護に欠かせない重要な役割です。
しかし、それだけでは人は本当には癒されません。看護が看護として成立するのは、その行為が「誰のために」「どんな思いで」「どんな関わり方で」行われているかという“関係性の質”が伴ってこそです。この「関係性の質」こそが、ケアリング(Caring)です。
ケアリングとは、
・相手の不安や痛みに気づき、受け止めること
・その人が大切にしてきたものを尊重する姿勢
・言葉にならない想いに耳を澄ませること
・その人のペースに寄り添うこと
・尊厳を損なわないように配慮すること
など、目には見えにくいけれど、看護という仕事の“心の核心(こころのコア)”を形づくるものです。
つまりケアリングとは、看護師自身の人間性や価値観、経験、優しさ、誠実さといった
「人としての力=人間力」そのものが介在して生まれる関わりなのです。
AIがどれほど発達しても、ロボットがどれほど正確に動作できるようになっても、このケアリングだけは決して代替することができません。
なぜなら、人の心は、人の心によってしか動かないからです。人の最期に寄り添うとき、相手の苦悩を受け止めるとき、その場に必要なのは“行為”だけではなく、「あなたがあなたのままでいていい」という深い承認のまなざしです。
看護学生の皆さんには、どうかこの“ケアリング”の価値を胸に抱いたまま、これからの実習や臨床に進んでいってほしいと願っています。
おわりに
来年も同じ学年に講義を行う予定です。ACPを“人生の対話”として受け取り、“その人らしい最期”を支える看護へとつなげてくれる人が一人でも多く育つことを願っています。
あなたたちの「人間力」が、これから出会う患者さんと家族の人生を支えていくことを、私は心から信じています。