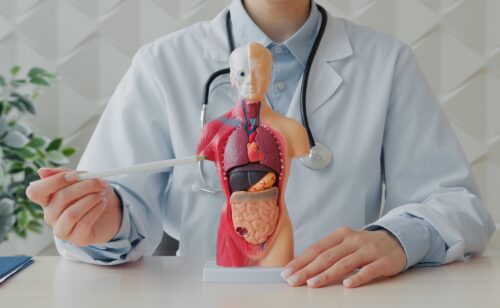「判断できなくなる前に」から「ともに考え続ける」へ
「認知症」という言葉が、日本の医療・介護の現場で使われるようになったのは、
2000年を過ぎて間もないことだったと記憶しています。
それ以前は、「痴呆」という言葉で語られ、どこか 仕方のないもの、どうにもならないもの として
扱われてきた時代でした。
やがて呼称が「認知症」に変わり、高齢者ケアの現場では、人生の最終段階まで、その人らしさを支えるという考え方が、少しずつ広がっていきました
終末期ケアのガイドラインが整い、「看取る」という選択が現実のものになった頃、私は現場で、避けて通れない現実に繰り返し直面するようになりました。
それは、人生の最終段階における意思決定の場面で、本人の意思や想いを知ることができないまま、家族が決断を背負わざるを得ないという現実です。
「では、認知症のある方の意思は、どこで、どうやって受け取ればよかったのか」
この問いは、
誰かを責めるためのものではなく、
また制度を否定するためのものでもありませんでした。
むしろ私は、認知症のある方の人生にとって、本当にふさわしい意思決定支援の在り方とは何か を、看取りを重ねる中で、考え続けるようになったのだと思います。経験こそが、私が“認知症における意思決定支援のあり方”に疑問を持つようになった原点でした。
現場で突きつけられた問い
認知症の方を看取るようになった現場では、必ず、ある局面が訪れます。
それは「食事がとれなくなる」という状況です。
これは、認知症に限ったことではなく、高齢期を生きる誰もが、人生の最終段階において
直面する可能性のある状況 です。
そして、医師から治療の選択肢が提示されます。
- 経管栄養
- 点滴
- あるいは、自然に任せる
そのとき、本人はもう、言葉で意思を示すことができません。家族は医師の説明を聞き、静かに、しかし深く悩みます。
「本人は、どうしたかったのでしょうか」
私はこの問いに、何度も、立ち尽くしてきました。
ACPがなかった時代の「空白」
今でこそ、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)という言葉があります。
しかし当時、その考え方は、まだ現場には存在していませんでした。
看取りはできるようになった。
けれど、その人の意思や想いを、どう受け取り、どうつないでいくのかという仕組みは、どこにもありませんでした。
本人の人生を大切にしたい。尊厳を守りたい。そう願えば願うほど、肝心の 「本人の声」が、どこにも残っていないという現実に、私は何度も立ち尽くすことになります。
この 「空白」 こそが、私の認知症ケアの実践の中で生まれ、そして今も問い続けている、原点です。
1.かつて認知症は「ACPの対象外」だった
少し前まで、日本の医療・介護の現場には、こんな空気が当たり前のようにありました。
- 認知症になったら、本人の意思はわからない
- 判断能力がないのだから、話し合っても意味がない
- 家族や医療者が決めるしかない
つまり、「認知症=自己決定ができない状態」と、ほぼ自動的に結びつけられていたのです。
この前提のもとでは、ACPはどう扱われていたでしょうか。
多くの場合、
「まだ元気なうちに書いておくもの」
「認知症になる前に済ませておくもの」
と位置づけられていました。
そこには、
「認知症になったら、もうACPはできない」という前提がありました。
この前提こそが、認知症ケアとACPを、長く切り離してきた最大の要因だったと感じています。
2.現場では、ずっと「声」があった
しかし実際の現場では、この前提に違和感を覚える人たちが、ずっと存在していました。
認知症のある人は、
- 何も感じなくなるわけではない
- 価値観が消えるわけではない
- 人生が突然なくなるわけでもない
言葉で説明することが難しくなっても、
- 表情
- しぐさ
- 行動
- 日々の選択
そこには、確かに「その人らしさ」 がありました。
「この人は、こういう関わりを望んでいる」
「これは、この人にとって苦痛だ」
そうした感覚は、日々関わる家族や支援者には、確かに伝わっていました。けれど制度や理論は、
その「声」を拾い上げる言葉を、まだ持っていなかったのです。
3.転機は「プロセス」という考え方
認知症ケアとACPが結びつく大きな転機となったのは、ACPが 「文書」ではなく「プロセス」 だと明確に位置づけられたことでした。
2018年、厚生労働省 の
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」改訂では、
- ACPは一度きりの決定ではない
- 状況や気持ちの変化に応じて見直される
- 対話を繰り返すこと自体が重要
という考え方が示されました。
この視点は、認知症ケアにとって決定的に重要でした。なぜなら、認知症は「ある日突然すべてが失われる病気」ではないからです。
4.「早期から」「ともに」考えるACPへ
ここで、ようやく現場の感覚と理論が、つながり始めました。
ACPは、
「判断能力がなくなる前に決めておくもの」ではなく、「その時々の力に応じて、ともに考え続けるもの」として捉え直されるようになったのです。
- 初期:本人の言葉を中心に
- 中期:本人の反応や表情を手がかりに
- 後期:これまでの人生や価値観をもとに
ACPは、
認知症の進行に合わせて形を変えながら続いていくプロセスだと考えられるようになりました。
この視点に立つと、認知症の人はACPの「対象外」ではなく、むしろACPが最も必要な人 だということが見えてきます。
5.「判断能力がない」という言葉の危うさ
認知症ケアとACPを考えるうえで、避けて通れないのが「判断能力」という言葉です。
確かに、医療行為や法的判断において、一定の判断能力が求められる場面はあります。
しかしそれと、
- どう生きたいか
- 何が苦しいか
- 何を大切にしてきたか
を感じ、表現する力とは、必ずしも一致しません。
「判断能力がない」という一言で、その人の人生全体を意思のないものとして扱ってしまうこと
こそが、最大の問題でした。ACPは、この問題に真正面から向き合う考え方だと感じています。
6.認知症ケアがACPを成熟させた
振り返ってみると、日本でACPが本来の意味に近づいてきた背景には、認知症ケアの現場があったと思います。
- 言葉に頼らない対話
- 日常の小さな選択を尊重する支援
- 家族と支援者が価値観を共有するプロセス
これらはすべて、認知症ケアが長年積み重ねてきた実践でした。
ACPは、その実践にようやく「名前」が与えられた概念だったのかもしれません。
おわりに:認知症になっても、人生は続いている
認知症とACPが結びついたのは、「認知症になったら終わり」という見方を、社会が少しずつ手放し始めたときでした。認知症になっても、その人の人生は続いています。
ACPは、その人生に寄り添い続けるための対話の姿勢 です。
私は、この視点を、これからも現場と言葉の両方で伝え続けていきたいと思っています。