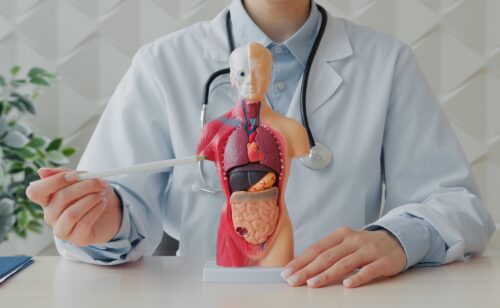〜Villaggio Fondazione Roma訪問記③|私が見た原点、日本への提言〜
ローマを訪れた目的のひとつが、この Villaggio Fondazione Roma(以下、ビレッジ)を自分の目で確かめることでした。
長年、認知症ケアに携わる中で私はずっと、「本来の認知症ケアとはどのような姿なのか」を追い続けてきました。制度の限界、マンパワー不足、家族の不安、現場職員の疲弊。日本の現場にいるほど、その問いは深まるばかりです。
そして、実際にビレッジを訪れて私は確信しました。「あぁ、やはりこれが認知症ケアの原点なのだ」 ここには、人が人として暮らし続けるための土台となる考え方が息づいていました。
しかし同時に、「日本がこの姿に到達するのは、現状では極めて難しい」という複雑な感情も湧き上がってきました。
この最終回では、私が30年以上、認知症ケアと向き合ってきた経験と、ローマで見たリアルな光景を重ね合わせながら、「認知症ケアの本質」そして「日本が進むべき方向性」を総まとめとしてお伝えします。

認知症ケアには「その人に合った環境調整」が必要
私はこれまで、北欧を含め多くの国の施設を視察してきました。
そこで必ずと言っていいほど語られたのが、次の考え方です。
認知症は一つのカテゴリーではなく、症状の表れ方・生活リズム・必要とする支援の質がまったく違うためです。こうした視点にもとづく支援は、より具体的に言うと次の2つになります。
● その人が“今できること”を生かす支援
● その人が“安心して過ごせる時間”を守るケア
この2つはどちらも尊重されるべき大切なニーズですが、同じ空間で同時に成立させることは非常に難く、どちらのニーズも満たしきれなくなる、それが現場で私が痛感した現実です。
日本では、制度や人員配置の制約から、“要介護度”という数字だけで分類せざるを得ないという状況が続いています。本来の認知症ケアには、生活背景、文化、価値観、人生史といった“その人らしさ”にもとづく環境調整が欠かせません。

生活が“本人の時間軸”で流れているという当たり前の尊厳
ビレッジでまず心を大きく揺さぶられたのは、生活の主導権が施設側ではなく、 “本人の時間軸”を中心に流れていること でした。
ここで大切にされていたのはただ一つ。「認知症になっても、その人が生きてきた生活スタイルは変えない」。その“支援の方針”が、日々の暮らしの中に自然に表れていました。
起きたいときに起きる。眠いときには眠る。
早起きの人は朝の空気を楽しみ、夜型の人は静かな夜をゆっくり過ごす。
お腹が空いたら、自分のペースでキッチンへ向かう。
他の住人と出会えば「おはよう」と挨拶を交わし、コーヒーを淹れる人、パンを温める人、それぞれが自然と役割を担っていく。
気持ちの向くまま外へ散歩に出る。
庭で季節の花を眺め、噴水の音に耳を澄ませ、ゆっくりとした時間を味わう。
誰かに“やってもらう時間”ではなく、
その人が自分のペースで日常を営んでいる時間がそこにはありました。
そこには決められたレクリエーションも、業務としての「お世話」もありません。
ただ、その人らしい一日が静かに流れている――そんな空気が満ちていました。
この光景は、「生活とは特別な“活動”ではなく、積み重ねてきた暮らしそのもの」という、ごく自然で大切なことを思い出させてくれるものでした。
日本の多くの施設では、“生活の軸”が施設側に移ってしまう現実
私が長く現場で働いてきた中で、ずっと胸に残っている違和感があります。それは、日本の多くの高齢者施設では、生活の流れがどうしても「施設側の都合」で組み立てられてしまうという現実です。
たとえば、日々の生活は次のように時間割のように管理されます。
- 起床時刻
- 排泄介助のタイミング
- 朝食の時間
- 入浴の曜日
- レクリエーションの開始時刻
これらは、決して悪意があるわけではありません。「安全の確保」「事故防止」「限られた人員で業務を回す」という事情から、施設側が生活の段取りを握らざるを得ないというのが実情です。
しかしその結果、本人が長年大切にしてきた生活リズムや価値観は、いつの間にか施設のスケジュールに置き換えられてしまいます。
たとえば、
- 朝食を食べない習慣の人でも、7時の朝食が当たり前のように提供される
- 毎日昼寝をしてきた人でも、「午後はレクリエーションです」と起こされる
- 散歩に行きたいのに、「今日は付き添える職員がいない」と制限される
こうして、“本人の生活の軸”が少しずつ奪われていくのです。
私は現場で働く中で、この「生活の軸を失うこと」が、残された力の消失につながる瞬間を何度も見てきました。
自分のペースで動けなくなると、できていたことが急にできなくなる。自分の時間で休めなくなると、感情が不安定になる。楽しみだったはずのことが、義務のように感じられてしまう。
施設運営の困難さも痛いほど理解しています。しかし、“本人の時間軸で生きられる環境”をどう守るかは、認知症ケアの根幹に関わるテーマだと、私はずっと感じてきました。

価値観と人生史で“暮らす場所”をつくるという発想
ビビレッジで特に印象に残ったのは、居住ユニットが進行度ではなく、その人がどんな世界で生きてきたか〈生活文化・階層・教育背景・職歴〉によって構成されている
という点でした。
ナースマネージャーの説明はとても明確でした。「認知症の進行度だけでは分けません。その人がどんな世界で生き、どんな価値観や文化をもってきたか。それが暮らし方にそのまま反映されるからです。」彼らが示してくれたのは、次の3つの生活文化圏でした。
● Traditional Style(伝統的スタイル/ブルーカラー)
工場勤務・職人・技術職など、実務・技能系の職を長く続け、
家庭的で素朴な生活リズムを大切にしてきた人たち。
● Cosmopolitan Style(国際的・教養スタイル/インテリ層)
大学卒以上の高学歴層で、語学・文化・芸術に親しみ、
知的な会話や文化的刺激が日常の一部だった人たち。
● Dynamic Work Style(ホワイトカラー/仕事中心スタイル)
会社員・専門職・管理職として働き、
明確な生活テンポと“仕事中心のリズム”を持ち続けてきた人たち。
ビレッジは、この“生きてきた背景”を尊重し、本人が慣れ親しんだ文化圏で暮らしを続けられるようにしています。日本では施設に入った瞬間、多様な人生が一つのグループにまとめられてしまうことがほとんどですが、ここでは、それぞれの人生史が“まるごと”受け止められ、暮らしに反映されていました。
「その人らしさ」はなぜ施設に入ると奪われてしまうのか ― 日本の構造的な課題
私たちは本来、自分の価値観や人生観に合うコミュニティを、無意識のうちに選んで生きています。誰と過ごすか、どこに住むか、どんな環境が心地よいか、それらはすべて“自分に合う世界”を自然に選び取ってきた結果です。ところが、日本の多くの高齢者施設では、施設に入った瞬間、その当然の選択感覚が失われてしまいます。
- どんな職業人生を歩んできたか
- どんな学びを積んできたか
- どんな文化に親しみ、どんな価値観で生きてきたか
- どんな生活習慣が身体に染みついているか
本来、暮らしを支える上で欠かせない“その人らしさの根幹”が、生活の環境づくりに反映されないまま、価値観の異なる人々が急に同じ空間で暮らすことになるのです。
これは日本の施設現場で長く働いてきた私自身、最も大きなギャップとして感じ続けてきた部分です。では、なぜ日本では「その人らしさ」を反映した環境づくりが難しいのでしょうか?
これは単に「現場の努力不足」ではありません。いくつかの構造的な問題が、深く影響しています。
① 介護保険制度が“同じ基準で人を分類する仕組み”になっている
日本では、ケアの提供は介護保険制度に大きく依存しています。制度上、利用者は 「要介護度」という数字で分類されるため、要介護2だからこのフロア、要介護5だからこのユニット、医療ニーズがあるからこの棟という“制度上の分類”が、実際の生活環境の分類にも反映されてしまいます。
しかし、要介護度は「身体の手間のかかり具合」を示すだけで、生活文化・価値観・人生史とはまったく関係がありません。結果として、“人生で育んできた世界が違う人たち”が、同じ空間で暮らすことになるのです。
② 職員配置が限界で、“生活文化に合わせたケア”をする余裕がない。
日本は慢性的な介護人材不足です。1ユニット30名に対し、日勤帯1名、遅番1名、早番1名、夜勤は2名というような環境では、利用者一人ひとりの“人生に合わせる”という発想がそもそも持ちにくいのです。結果として、“安全・効率を優先する”しか選択肢がなくなってしまうという現実があります。
③ 「事故を起こしてはいけない」という法的・社会的プレッシャー
日本では、転倒事故や外出トラブルが起きると、施設側が強く責任を問われます。そのためどうしても、外出は制限、散歩も制限、夜間の離床も制限、朝の生活リズムも管理という“守りのケア”に偏りやすいのです。結果として、自由や尊厳よりも、事故防止が優先される文化が根強く残っています。
④ 「認知症だから分からない」という社会の誤解がまだ残っている。
私が過去に耳にした、忘れられない言葉があります。「認知症の人はどうせ分からない。」この一言には、日本の介護現場に深く根を張る“誤解”が凝縮されています。もちろん、悪気があって言っているわけではありません。むしろ、多くの人が抱いている素朴な“思い込み”なのだと思います。しかし、この思い込みは、結果としてこんな価値観につながってしまいます。
「認知症の人は、細やかな配慮をしても気づかない」「好きだったものやこだわりは、もう意味をなさない」「まずは安全に預かってくれればそれでいい」そんな誤解が、ケアの質を下げる大きな原因になっています。
日本が進むべき未来へのヒント
ローマで見た「その人の人生をそのまま受けとめるケア」は、決して特別なものではありませんでした。むしろ、認知症になっても人として当たり前に暮らし続けることを守る文化そのものだったのです。もちろん、日本で同じ形をすぐに再現することは難しいかもしれません。けれど、そこで学んだ本質は、必ず日本の未来を照らすはずだと、私は強く感じました。
ここで、今回の視察と自分自身の40年の現場経験から、日本の認知症ケアに必要だと改めて確信した6つのポイント をまとめます。
① 認知症の本質理解を深める教育
認知症は「人格の喪失」ではありません。“何ができなくなったか”ではなく、“何が残っているかをどう支えるか”が本質 です。これは、社会全体が教育を通して学んでいく必要があります。
② ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の普及
その人の人生観、諦めたくないこと、大切にしてきた生活の軸。それらを“本人の言葉”として共有し、本人を中心にしたケアや意思決定を積み重ねていくプロセス。私はこれを日本で広げることが、これからの重要な課題だと考えています。
③ 医療モデルから生活モデルへの転換
治療中心ではなく、「その人の暮らしを守るケア」 へ軸を移すこと。病名よりも暮らし方、症状よりもその人の時間。医療と介護の境界を越えていく発想が求められています。
④ 家族と現場の双方の教育
家族も、介護者も、地域も認知症を深く理解すれば、“その人らしく生きられる時間”は確実に増えます。教育は支援の出発点です。
⑤ 完璧より“尊厳を守る覚悟”
リスクをゼロにしようとすれば、自由・選択・楽しむ気持ちまでゼロになってしまう。完璧を求める必要はありません。大切なのは、その人の尊厳を守る覚悟を持つこと。ローマのビレッジでは、その姿勢を強く感じました。
⑥ 大きな改革より“小さな自由”を増やすことから
ビレッジのような施設を日本で一気に作ることはできません。でも、小さな一歩ならすぐに踏み出せます。
- 朝の時間を少しゆるめる
- 散歩の時間を“その人のペース”に合わせる
- 飲み物を自分で選べるようにする
そんな 小さな自由の回復 が、本人の世界を確実に変えていきます。
おわりに
ローマで見たビレッジは、決して特別な最新式の施設ではありませんでした。そこにあったのは、人が人として最後まで生きるための“当たり前”を守るケア でした。
認知症になっても人生は続きます。尊厳は失われません。その当たり前を社会が思い出すためには、現場で働く者が声をあげ続け、学びを共有し続けることが欠かせないと、私は改めて感じました。
ローマで目にした光景は、日本の未来へのヒントであり、確かな希望でもありました。これからも私は、40年の現場での学びと、今回ローマで得た気づきを胸に、認知症の人の理解とケア、意思決定支援のあり方、そして ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の大切さを、丁寧に伝え続けていきたいと思います。